ライティングに関わる人に役立つ情報をお届け


2024年に創立150周年を迎えた青山学院は、幼稚園から大学までを擁する学校法人です。青山学院と聞くと、都会的でおしゃれなイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。同法人は、青山学院の魅力や歴史を独自の観点から紹介するWebメディア「アオガクプラス」を運営しています。
今回は、本メディアを担当する広報部広報課課長の髙木茂行さんと主任の山東亜希子さんに、メディア設立の経緯や記事作成にかける思いについて話を聞きました。


髙木さん:幼稚園、初等部、中等部、高等部、大学、大学院、専門職大学院が所属する今年創立150周年の総合学園です。東京の渋谷に本部があります。明治時代にキリスト教の宣教師の方々が作った3つの学校をもとにしているため、キリスト教主義です。学生を育てるにあたっては、これからの世の中のためになる人材としてサーバント・リーダー(※自分の使命を見出して進んで人と社会に仕え、その生きた方が導きになる人)になってもらうことを目標としています。
関東大震災の際には建物を解放して被災者の救助に当たり、慰問袋を持って地域の方に必要な物資を配布しました。東日本大震災のときも体育館を解放し、帰宅困難者の方々を受け入れ、広域避難所としての役割を果たしました。このような歴史をもった総合学園として、社会のためになる活動を続けるうえで、中心となるような人材を育てることに注力しています。
山東さん:青山学院についてもっと深く知ってもらい、興味を持ってもらうことがミッションです。読者に楽しんでもらうことで、イメージアップに繋げたいと思っています。本学に通いたいと思う受験生を増やし、在校生や保護者の満足度を上げ、学内外にファンを作りたいですね。

髙木さん:広報部の6名で取り組んでいます。年に4回、公式機関紙である「青山学報」を発行していますが、学院の広報誌ですので当然、編集委員会という組織のもと、オフィシャルな内容で構成され、記載できるページ数も限られます。それに対し、アオガクプラスでは広報部のメンバーの好きなこと・興味があることを中心に企画を立て、書きたいだけ書くようにしていますね。
メンバーの一人が提案した企画を、皆で話し合いブラッシュアップします。企画が固まったら設置学校の先生方や生徒さんにアポを取り、取材へ。記事の作成はもちろん、撮影やCMSの入稿、校正まですべて自分たちで行っています。すごく労力がかかりますが、徹底的に自分たちでやるのが広報の仕事だと思っているんです。現在の記事総数は、303本になりました。とても楽しくて、幸せな仕事です。
山東さん:基本的に学院の中にある好きなこと、興味のあること、おもしろいと思うことを追求して企画を立てています。たとえば、青山学院に対して都会的なイメージがある方が多いと思うんですが、実際に訪れてみると鳥がさえずっており、緑が溢れていて、都会のオアシスみたいなところなんです。その緑の美しさについて記事にしたいと思ったのですが、それだけを紹介してもつまらない。そこで、大学の英米文学科の先生と宗教センターの先生、中等部の先生と生徒を誘い、植物とキリスト教を交えながらキャンパスの自然を見て回るという企画を立てました。
そして完成したのが「青山学院の四季彩-グリーンパーティーへようこそ-」というシリーズです。本シリーズの裏テーマは、キャンパスの中の食物(植物)を子どもたちに知らせるということ。災害時に学校から出られなくなったとして、キャンパス内に食べられるものがあると思ったら心強いじゃないですか。ビワや梅とかもあるんです。そのことを子どもたちに編集したいという気持ちがありましたね。
山東さん:当学院は「英語の青山」と呼ばれるように、語学の勉強を目的に通学している学生も多いです。ところがコロナ禍においては、海外に行く機会が激減しました。学生たちが語学を身につけるモチベーションが下がるのではと、心配になったんです。そこで海外に行けない鎖国時代にオランダ通詞になった方、鎖国時代に語学の勉強をしていた方たちの物語を知れば、学生たちのモチベーションを上げられるかもしれない。通訳翻訳専門の英米文学科の先生にオランダ通詞について連載いただくよう、依頼しました。初めは「専門家の先生は他にもいらっしゃるから」という理由でご遠慮されたのですが、粘りに粘ってなんとか協力してもらえることになりました。それが「美しき陰翳」シリーズです。
髙木さん:私は本大学の史学科卒業のため、「アオガクタイムトラベラー」という学院の歴史を楽しみながら知ってもらえるような読み物を作っています。ある日、「外国の方から表札の“University”のスペルが間違っていると言われた。英語の青山と呼ばれているのに、まずいのではないか?」と電話がかかってきたんです。そんなばかな、と思って確認しに行くと“Unibersity”と本当に書いてあるんです。なぜこうなったのかを徹底的に調べた記事が「スペルミスの大失態? Unibersity!?【アオガクタイムトラベラー】」です。
髙木さん:2019年に立ち上げてしばらくは、あまり注目されていませんでした。しかし、記事を少しずつ増やしていくうちに、教職員から感想をもらったり、広報担当の理事から卒業生に広めておくよと言われたりすることが多くなりましたね。先生や関係者を巻き込み当事者意識を持ってもらうことで、応援してもらえる環境づくりをしています。
さらに、アオガクプラスの噂を聞きつけ、記事を寄稿してくれる方もいます。ロサンゼルス在住の国際科学編集者連盟執行理事である及部泉也さんから「青山学院には明治時代に気象学の研究をしていたすごい人物がいる。その方についての記事を書かせてほしい」という連絡がきました。そして執筆してもらったのが「明治時代の気象学の先駆者、田村哲」という記事です。アオガクプラスを運営していたからこそ生まれた接点だと思います。
髙木さん:汚い言葉を使わず、上品さを保つことです。青山学院のイメージを壊さないようにしています。また、そのときに話題になっていることと青山学院を関連づけて記事にするように意識しています。津田梅子が新札になると話題になったときは、当学院の設立に携わった津田梅子の父親の津田仙にまつわる記事を出しました。
山東さん:写真を多めに入れたり、何度も推敲して可読性を上げるようにしています。
髙木さん:各設置学校間でコミュニケーションを取っている様子を、積極的に記事にして広めたいと思っています。さらに、在校生をもっと巻き込みたいですね。著名な卒業生に対してはすでにインタビューをしているので、一般の方にも注目したいです。また、キリスト教に親しみを持ってもらえるような記事を増やしたいと思っています。今後も各設置学校や自治体と連携しつつ、青山学院の歴史を残していきます。
TEXT:ゆう

 人気記事ランキング
人気記事ランキング お役立ち情報
お役立ち情報
 WEB MEDIA GUIDE
WEB MEDIA GUIDE
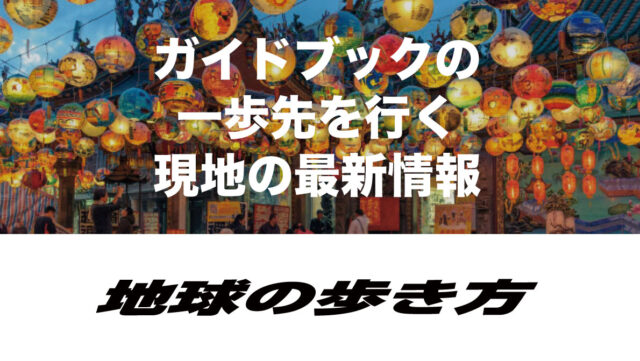 WEB MEDIA GUIDE
WEB MEDIA GUIDE
 インタビュー
インタビュー
 WEB MEDIA GUIDE
WEB MEDIA GUIDE